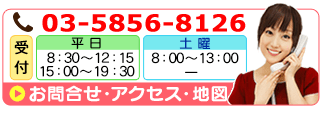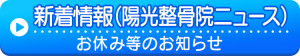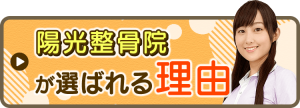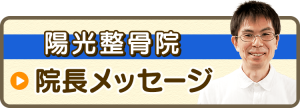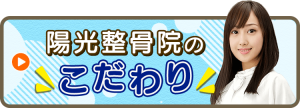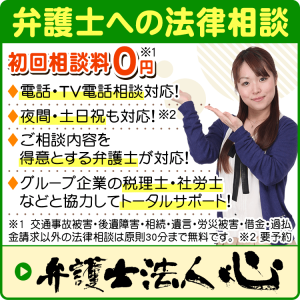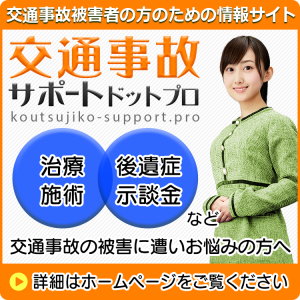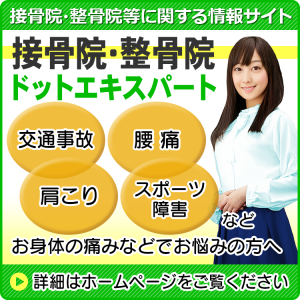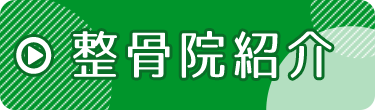急性痛と慢性痛の違いについて
1 痛みの種類は大きく分けて2種類
痛みは「急性痛」と「慢性痛」の大きく2種類に分類されます。
突然のケガなどによって痛みが生じ、短期間で回復するものを「急性痛」と呼んでおり、それに対して、ケガが治ったあとに長期間に渡って痛みが続くものが一般的に「慢性痛」と呼ばれています。
2 急性痛の特徴
急性痛は文字通り、急なケガや病気などが原因で生じる痛みです。
例えば、日常生活での転倒による打撲や、スポーツ中の肉離れ、事故による捻挫等を原因とする痛みは、急性痛に分類されます。
主に一過性のもので、ケガが改善すると、痛みも治まります。
痛みを取り除くために適切な施術を受けることが大切ですので、急性痛でお悩みの際は整骨院などにご相談ください。
3 慢性痛の特徴
慢性痛は、痛みの原因がハッキリしないものの、痛みが長く続いている状態を指します。
局所的に痛むのではなく、「何となく痛みがある」「このあたりが痛むような気がする」など、痛みの範囲が曖昧なことも多いです。
そのため、慢性痛が不安を引き起こしたり、痛みがあるため普段と同じパフォーマンスができずストレスを感じてしまったりと、気持ちの面にも影響を及ぼすケースが少なくありません。
不安な気持ちやストレスが、さらに痛みを強く錯覚させる等、悪循環に陥る場合も考えられます。
まずは、信頼できる通院先を見つけ、どういった痛みで悩んでいるのかを相談するとよいかと思います。
4 急性痛も慢性痛も適切な施術を受けることが大切
急なケガは、初期に適切な処置を行い、施術を受けるかどうかが予後に大きく影響します。
ケガの痛みを放置することで、その痛みが慢性痛になってしまうおそれもありますので、まずはお早めに適切な施術をお受けください。
慢性痛の場合も、「いつものことだから」と痛みを軽視してしまい、通院せずにそのままにしてしまうことがあるかもしれませんが、適切な施術を受けることで少しずつ痛みが改善する可能性がありますので、諦めてしまわずに、まずは適切な施術を受けることが大切です。